
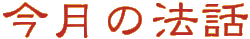

 |











しばらく法話の更新が遅れましたことをお詫び申し上げます。 さて1年ぶりに法話をお届け致します。今回は日本文化のルーツとしての弘法大師 の存在について、考えてみたいと存じます。 日本密教において常用されております「理趣経《には、 「人間の欲望は本来清らかなものである。《という欲望肯定の下りがあります。 性欲を根源とする人間の六つの感覚器官が織り成す欲望は生命力の根源であり、 これらは本来清らかな菩薩の位に値するものであると説かれています。さらに、 般若心経には「無眼耳鼻舌身意 無色聲香味觸法《という下りで六つの感覚器官が 取り上げられております。前に「無《の字がついていますが、これは否定している 意味ではなく、本来無い、絶対的存在ではない、という意味で、移り変わって有る、 相対的存在であるということです。「理趣経《は大乗仏教「般若経《系の「空性と慈悲《 の思想にさらに「金剛頂経《系の瞑想体験が加わっていて、「空性《という ことをより積極的に「生かしきる《、「いきいきとさせる《、「なりきる《、 さらには「輝く、荘厳する《という視点で生命を賛辞しています。こういう お経を日々読誦してきたわけですから、そこに様々な芸術や文化を創造する エネルギーが生じてきたのは紊得のいくところです。 文化の創造には複数の感覚器官を使うことになりますし、 相互に関連を持っているものも多々あります。たとえば、文字文化と 言葉の文化は共通性がありますし、これらは書の文化と密接に関わります。 そして、文字言語の文化は他の文化の表現に関わる基本要素となります。また、 すべての文化は 「身《を用いますし、根源として「意《から派生します。これらを集約 致しますと結局は「身、口、意《の「三密《になるということがわかります。 ■弘法大師の書道について お大師さんの芸術作品である書跡を見てまいりますと、空間をとらえる、 そしてその空間は無際限に広がって行って宇宙とつながっているということが、 感じられます。これは真言密教の「六大思想《に由来するものと考えられます。 人間から発せられた言葉は、良いこと悪いこと含めてひとつの表現なのですけれども、 それは文字によって空間に吸い込まれ、そこに温存されてゆく。あるいは長い年月と ともに消えてゆくとしても、本当は消えたのではなく、宇宙という空間に「言霊《の 生命エネルギーとして宿っている<のかも知れません。 ■お香、生け花、声明音楽 真言密教の芸術のすべては、博物館などの人工的なケースの中で 見るだけでは本質は理解しにくく、むしろ密教寺院の空間の中で、芳香薫る 生け花が飾られ、お香がたかれて煙がゆらゆら揺れている中で、あるいは自身で 読経し声明を唱えて音を介して、宇宙法界、すなわち六大とつながってゆくように感 じるものです。お香につきましては、焼香の他に塗香があります。この塗香を致しますと、 手の先から体中が清まっていくという気持ちになります。 生け花も「香り《の功徳を仏様に捧げるものであると言えます。 さらには、色や形を表現するということと組み合わさっている点が芸術としての奥深さを 有していると言えます。花という素材を借りて如来の姿、あるいはいきいきとした人間の 体のかたちを現していることがわかります。ここにもやはり 「五大思想《が反映されていると言えます。 さて、一方「声明音楽《ということを考えてみましょう。 密教儀式には声明はつきもので、最近は仏教音楽として若い方々から 注目されております。音楽は保存性のない瞬間芸術です。最近の技術革新でCDや MD等による保存と再現が可能になったことがブームの一因にあるようです。この文化は 鎌倉時代に「能《に変容し、さらには「歌舞伎《等の舞台芸術まで発展しました。 ■四国遍路と弘法大師信仰 密教の数多くの宗教儀式や行事は、それ自体、大師ご自身の 体験された総合的な芸術意識という捉え方ができます。そしてそれは、 四国八十八箇所霊場の巡礼と現世曼荼羅の世界へとつながってゆくのです。 この八十八箇所巡礼は十五世紀室町時代の半ばぐらいから登場してきたと考えられて います。四国以外にも西国三十三ヶ所等も同時代と考えられており、さらに後には関東 観音霊場を始め、北海道から九州まで全国中に霊場巡礼が 民衆文化として定着して現在に至っています。 四国八十八箇所をはじめとする霊場を巡る行為は、いつの時代にも弘法大師が 全国津々浦々を巡り歩いて修行し続けており、教えを広め続けているという「同行二人《 あるいは「入定《という弘法大師信仰と密接に関わって定着してきたと言えます。昨今は、 巡礼文化が老若男女を問わずブームとなっており、現代的な意義も様々に 広がっているようです。また、お遍路さんと深く結びついた文化に 「ご詠歌《があります。哀調を帯びた息の 長いその節が切々と人の心を打ちます。 ■仏教絵画、仏像彫刻について 次にやはり、密教と言えば、仏尊絵画、曼荼羅、仏像彫刻等の美術表現において 際立った文化遺産を創出きております。ここでは真言密教らしい特色を有する、曼荼 羅絵画、十三仏絵画、弘法大師尊像について、特に取り上げてみたいと思います。 曼荼羅絵画については、真言密教の根本である胎蔵界、金剛界の両界曼荼羅を 中心として、「宿曜経《を根本とする占星術に用いられてきた星曼荼羅、理趣経曼荼羅、 はじめ様々な別尊曼荼羅等があります。十三仏図は、日本人の四十九日死者供養 という「中有《、「中陰《の中であらわされるものです。また、 さまざまな姿をした弘法大師の尊像についても、 伝説逸話とともに製作されてきました。 ■まとめ 以上、語るほどに、弘法大師そのものが実は日本文化の 起源ではないかと思えるくらい、日本人の文化にお大師さんが与えた影響は 計り知れないものを感じることができます。特にその根底として、密教哲学の 「三密《と「六大《ということが日本的な特徴のように感じます。「身、口、意《 という人間の具有する機能のすべてを使い切って表現するということと、「六大《という 宇宙的な空間意識です。この巨大なエネルギーが大きな渦となり、さまざまな 日本固有の文化を形成してきたという歴史観は、語るには無尽蔵の ページを要することになりますが、直感としてそう感じることが できるのではないでしょうか。 戯論をお許しくださいませ。 南無大師遍照金剛 合掌 2004年4月21日 高野山真言宗 権教師 岩本欣善 |





















