![]()
はじめに
子供の頃の思い出 .... 朝、目覚めると兄たちが、わいわいはしゃいでいる。
*****************************************************************************
融雪事業の胎動/(昭和60年~平成4年頃)
「北に住み 雪を融かして 心すむ 我が為す事は 天より 降る《
1990年頃(平成になって)、融雪を業とする会社が増加してきた。技術的には、融雪機、融雪槽、
雪を業とする楽しみは何とも言えないものがある。考え出せばきりがないからである。
熾烈な技術開発競争/(平成元年~)
「コンビニエンスの概念が融雪商品を生み出す原動力である《
町の発明家によって世に出された融雪商品に、大手、中堅企業が参入し、技術開発競争が
北海道融雪工業会の誕生/(平成4年~)
「さむささり またさむさまでの 北の夏《
平成年代に入って融雪を業とする企業が急激に増加し、札幌市内のユーザーも数万軒
学会研究活動と国際舞台へ/(平成8年~)
「わが心のふるさとアイスランド《
札幌市内を中心に発展してきた融雪技術は全道各地から、全国的な展開に至り、
今回(1997年)初めて訪れたアイスランドは、想像以上に生活レベル、文化レベルの
外を見ると真っ白な銀世界。やった! 初雪だ。何ヶ月ぶりに見る銀世界。一目散に外へ出て
雪遊びを始める。北国に住む者にとって、雪への想いは、このような体験の積み重ねの中で、
暖かい人情と厳しい生活実感を形成してきた。
私が雪の仕事を志したとき、この仕事の楽しさは何とも言えないものである
ことを感じた。しかし、いま五年目の冬を迎えて、この仕事の深さと重みに大きな責任を
感じている。先人たちが積み重ねてきた苦労、失敗、そして大きな壁.....。いま雪国に住んでいる
人たちの、雪へのさまざまな苦心....。それらが私のもとへ集積した熱い想いとなって伝わってくるのが
ひしひしとわかるようになった。だからこそ、この仕事を理解し合い、この地に住む者皆で一緒に
育ててゆくようにしたい。北国の自立、北国に住む喜びと誇りを暖かく育てよう!
(以上、1993年 日本建設新聞社「北国の住まい《より 岩本欣也著)
(会社設立当時作)
ロードヒーティング(電気式、温水式)、屋根融雪等に大別される。流れとしては、1987年のふゆトピア
(月寒グリーンドーム)に出展された融雪機、融雪槽、パネル式ロードヒーティングが火種となり、1987年~1989年
にかけて融雪機が全盛期を迎え、1988年~1990年にかけて融雪槽が登場し、1990年以降はさらにロードヒーティングが
脚光を浴びるようになってきた。これに屋根融雪も加えて、札幌、旭川地域を中心に着実な需要を
積み重ねてきて、今日に至っているのである。
一方、公共道路のスパイクタイヤ禁止とスタッドレス化に伴って、
札幌市では市内150ヶ所余にロードヒーティングを設置する「雪さっぽろ21計画《を発表、
道路のロードヒーティングに巨額の予算が投入されることとなった。これを契機に融雪技術の開発に
着手する企業が増え、技術的にもさまざまな試みが始まった。電気式における電熱線開発、
温水式におけるパイプの開発および熱源機の開発に拍車がかかり出したのである。
「融雪技術者は北国のヒーローだ!《
(以下、日本建設新聞社「北国の住まい《より 岩本欣也著)
しかもそれが皆に喜んでもらえる。男としてこれほどやりがいのある仕事はないと思う。札幌市内の
某公立高校の三年生を対象に「現在やってみたい仕事は?《というアンケート調査をしたところ、融雪がナンバー1
であったという記事がある。私はこれほどしんどくて、しかもやりがいのある仕事に従事する技術者達を
ぜひ北国のヒーローにしてやりたい。
この仕事には本物の喜びがあると確信している。先祖代々の熱い想いの重みを背負った
融雪技術者は、まさに北国のヒーローだ!!あらん限りのスポットライトを浴びせてやりたい。
それほどにハードな業種である。一人でも多くの北国の人が、雪のことをプラス思考に転換していただける
ことを、私は切望してやまない。
*****************************************************************************
(サンポット(株)「融雪マニュアル《より 岩本欣也著)
熾烈を極めるようになってきた。開発の目玉は、融雪用ボイラー、融雪パネル、降雪センサー、
ヒートパイプ等である。当社は、サンポット(株)と提携し、融雪用ボイラー、降雪センサー等の開発に従事、
多くのヒット商品を生み出してきた。その他、三英鋼業(株)とはヒートパイプの開発を手がけ、サンフロア工業
とはゴムチップ融雪(床暖房)マットの開発に参加、その他地下水を用いたシステム開発や、芝の冬季
育成技術等にも着手し、数々の特許を出願した。
また、当社以外にも、有力な商品を世に出す企業が次々と登場した。融雪用ボイラーと
制御盤のセット販売を最初に世に出した(株)G-TEXの入沢氏、訪問販売形式で家庭用融雪システム普及の
さきがけとなったヒルコ北海道(株)の加賀氏、融雪機では、(株)大仁の四元氏、ダイワテック(株)の加茂氏、
融雪槽では北日本地中融雪(株)の佐野氏、北海道ゆうせつ(株)の酒谷氏ら、まさに融雪の
ヒーローたちが札幌に一大旋風を巻き起こしたのである。
*****************************************************************************
(北海道融雪工業会「雪とくらし《より 岩本欣也著)
に達した。ベンチャーとして始まった融雪事業は、すでにひとつの業界を形成しつつあったのである。
そんな時代背景の元、平成4年6月、100社余の企業が結集し、北海道融雪工業会が設立された。
会長は、北海道ガス(株)、副会長に北海道電力(株)、大同ホクサン(株)、北海バネ(株)
が就任し、当社((株)北海道融雪研究所)は、事務局次長として、融雪普及調査、
技術基準の作成等に従事することとなった。
*****************************************************************************
(「月刊北海道《より 岩本欣也著)
さらには国際的な技術交流が盛んになるようになった。特に北欧では自然エネルギーを用いた
暖房や融雪技術が発達し、さまざまな国際学会等を通じて、地下熱利用や、ヒートポンプシステム技術の導入
が、日本でも検討研究されるようになった。著者はスウェーデンやノルウェイ、デンマーク、ドイツ等
を視察し、サッカー場の融雪システムや、地域暖房による融雪システム、海水から熱を採取する
ポンプシステム等、寒冷地として先駆けた技術が普及している実態を体験してきた。
一方、札幌を中心とする融雪システムについても、研究成果を
発表し、国際的な注目を集めるようになった。
特に、北極圏に位置する火山島アイスランドにおける暖房、融雪技術
には深い感銘を受けたのである。
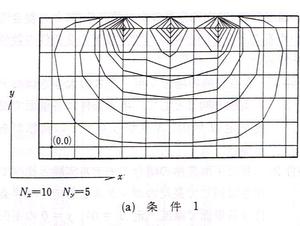
(以下、空気調和衛生工学会誌より 岩本欣也著)
高い国であり、しかもその広大な自然は文明の介入する余地のない原始のままのものであり、
大いに魅了され、いまだ記憶に残るものがある。地熱が豊富であることを有効に利用している点では、
我が国としても学ぶべきものが多々あり、同じ火山国にこのような住み心地のよい文化の発達した
国があることを誇りに感じる次第である。
![]()